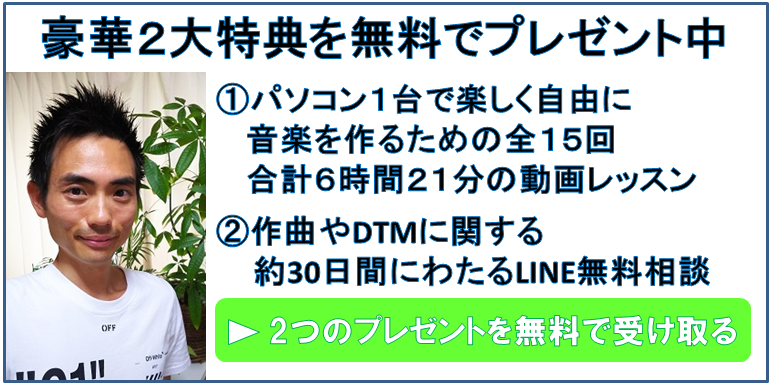耳で聴いた音楽を、DAW(作曲ソフトのこと)などで再現するのが耳コピー、通称「耳コピ」です。
これをやると、作曲ができるようになったり、聴いた曲の中身が手に取るように分かって自分の作曲の幅が広がるなど、様々なメリットがあります。
ただ、耳コピは非常に地道な作業で根気が要ります。
僕も何年も耳コピをしながら、やりやすい方法を研究してきました。
そして、耳コピが超やりやすくなる方法や、耳コピの手順が分かるようになりました。
この記事を読むことで、大変だった耳コピの作業がかなりやりやすくなります。
本記事では、僕が普段、DAWで行っている具体的な耳コピのやり方を紹介します。
DAWを使ったオススメの耳コピ方法
耳コピにはいろいろな方法がありますが、僕は普段、DAWに耳コピしたい音源を読み込んでやってます。
これによって、物凄く耳コピがやりやすくなります。
コピーしたい音源を聴きながら、それをメロディやリズムをなぞるように打ち込みをしてく感じです。
音源をDAWに読み込んでおくことで、耳コピしたい曲と自分が打ち込んだ譜面を常に比べながら進めることが出来、すごくやりやすくなります。
これは、例えるなら絵を透かして写す作業に似ています。
憧れの絵を上手に真似して描くには、真似したい絵の上に裏が透けて見える紙を乗せます。
そして、透けて見える絵をなぞれば、上手に絵を描くことができます。
これと同じように、耳コピしたい曲を流しながら、それをなぞるようにメロディやリズムを打ち込むのです。
曲を聴きながら、自分の打ち込んだメロディやリズムが合っているか、答え合わせがすぐできるので便利です。
それでは、実際にどんな風にやっているか説明します。
プロジェクトを作成する
まず、DAWの作曲データを保存するプロジェクトを作ります。
プロジェクトとは、作曲ソフトで入力したデータを保存する基本的なファイルです。
トラックを作成する
次に、メロディやリズムを打ち込むトラックを作成します。
トラックとは、DAWで作曲や編集をするときの基本単位です。
ロックバンドの基本構成である、ボーカル、ギター、ベース、ドラム。そしてボーカルに対するハモリのコーラス、計5つのトラックを作ります。
もちろん、これ以上のトラックが必要になることがほとんどですが、後から追加できるので問題ありません。
音色設定をする
作成した各楽器の音色を設定します。
とりあえず、それぞれの音が聞き分けられればいいです。
そのため、ハイクオリティな音色にする必要はないです。
DAW付属の音色で、それぞれの音色を選んでおきます。
耳コピする音源を取り込む
次に、耳コピしたい音源をDAWに取り込みます。
通常、配信されている音源って、mp3形式になっていることが多いです。
もし、DAWでmp3形式が読み込めなかったら、wav形式などの読み込めるものに変換します。
僕は、RealPlayerという無料ソフトで変換しています。
DAWへの読み込みは、ドラッグ&ドロップでもいける場合があります。
テンポを設定する
次に、作成する曲データのテンポを設定します。
このとき便利なのが、メトロノームのようなクリック音を出せる機能です。
音源を再生しながら、クリック音のテンポと同じくらいになるように設定します。
各楽器の音を聴いて打ち込む
後は、やりやすい音から、メロディやリズムを聞き取って打ち込んでいきます。
おすすめは、ボーカルもしくはドラムパートです。
ボーカルは、メインメロディなので最も目立つので聞きやすいです。
また、ドラムは根幹となるリズムを刻んでいて、これも比較的聞き取りやすいです。
ボーカル同様、ギターはイントロや間奏でメインメロディを担当していることが多いので、そちらもおすすめです。
耳コピのコツ
以下、より効率的に耳コピを進めるコツを紹介します。
範囲指定をしてリピート再生する
耳コピでは、同じ部分を何度も繰り返し聞きます。
そのとき、いちいち曲を停止して、ちょっと戻って再生…ってやってたらめんどくさいですよね。
そこで、DAWの再生範囲を指定する機能を使います。
再生範囲を指定しておけば、耳コピしたい箇所に絞ってずっとリピートしてくれます。
最初は、1小節、なれたら何小節か繰り返すといいでしょう。
口ずさみながら、打ち込む
耳コピのポイントとしては、聞いたメロディを歌いながら打ち込むとやりやすいです。
自分で歌えていれば、音程が分かっていることになります。
声を出して、その音と同じ音程を見つけて打ち込んでいきましょう。
曲を流しながら、なぞるように打ち込む
また、曲を流していると縦のバーが右側に流れていきます。
慣れないうちは、その流れに沿って、なぞるようにメロディを真似して打ち込んでいくといいです。
冒頭に紹介した、真似したい絵を透かしてなぞるイメージです。
曲のリズムに合わせてボタンを押す、音楽ゲームのような感じといってもいいですね。
ちなみに僕はめちゃくちゃ音源ゲームをやってました。
パターンを見つけたら、コピーする
ドラムのリズムなどは、特に繰り返しが多いです。
そのため、1小節~4小節くらいで繰り返しパターンを見つけたら、どんどんコピーしていきましょう。
ミキサーを活用する
DAWには、各トラックの音量などを調整するミキサー機能があります。
ミキサー機能を使って各楽器や耳コピしたい音源の音量を調節することで、耳コピがやりやすくなります。
また、各トラックの「M」ボタンがミュートボタンです。
これを押すと、そのトラックの音が鳴らなくなります。
逆に、「S」ボタンがソロボタンです。
これを押すと、そのトラックの音だけ鳴らすことができます。
複数のトラックのSボタンを押せば、それらのトラックの音だけがなります。
MボタンとSボタンをうまく使えば、耳コピしたい音だけ鳴らして音を聴くことに集中することができます。
逆に、打ち込んだ音だけならして、音程やリズムを確認することができます。
ある程度打ち込んだら、自分の打ち込んだ音と耳コピしたい音源を両方ならしてみて、違和感がなければOKです。
予測して打ち込む方法もありますが…
上記で紹介したコツの他にも、音楽理論を学んで、パターンやセオリーに当てはめて次にどんな和音が来るか予測して打ち込む方法もあります。
メジャーな曲の場合、コード進行と呼ばれる和音の進め方に一定のパターンがあることが多く、予測して打ち込むことで極めて作業時間を短縮することができます。
曲から譜面を作るのが耳コピの目的の場合、理論に沿って予測して打ち込んでいくのは効果的です。
しかし、自分の作曲センスを高めたり、アレンジの引き出しを広げるなどの目的で耳コピをする場合、予測して打ち込む方法に頼りすぎるのはオススメできません。
なぜなら、自分の知っているパターンに当てはめてしまうため、音楽を深く聴くことから離れてしまうからです。
このため、自分が耳コピをする目的に応じて、方法を選んでいくのがいいです。
まとめ
ここまで説明してきたように、DAWに耳コピしたい音源を取り込んで、それをなぞるように打ち込むをするとやりやすいです。
是非、試してください。
僕のサイトではこの記事以外にも、Cubaseの操作方法について詳しく解説した記事を数多く掲載しています。
ただ、個別の記事を読んでいてもなかなか全体の流れはつかみづらいと思います。
そこで、
僕のサイトに載っている知識やテクニックを、順番に見ていくだけで学ぶことができる
Cubaseで思い通りの音楽を作るための合計15本の動画レッスンを無料でプレゼントしています。
5年以上の時間をかけて僕が培った、DTMの作曲ノウハウをすべて説明した、他にはない大ボリュームの動画レッスンとなっています。
僕自身、専門的な音楽の勉強や楽器演奏の経験の無いところから、社会人になって作曲ができるようになりました。
そのため、一切経験がない方でも安心して見ることができる内容になっています。
作曲に興味をお持ちでしたら、是非チェックしてみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。