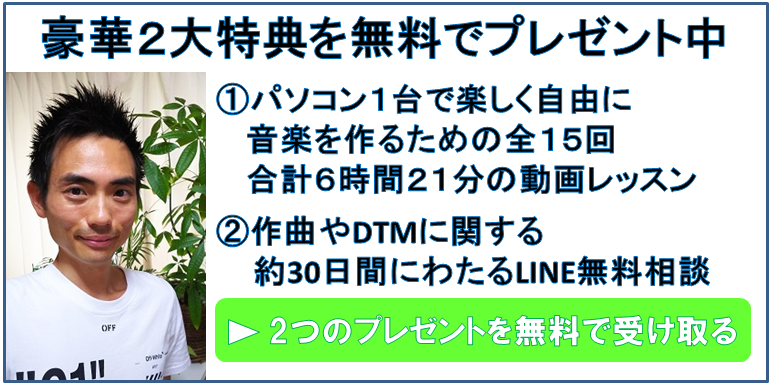DTMでエフェクター(エフェクトと同意)を使うとき、インサート方式とセンド方式を使うことができます。
僕は、最初インサート方式でしかエフェクターを使っていませんでした。
しかし、センド方式を使うと様々なメリットがあると、DTMを勉強する中で分かってきました。
インサート方式とセンド方式の違いは、「元の音声信号を残すことができるかどうか」です。
これらの違いについては、以下の記事で詳しく記載しています。
今回は、センド方式を使う場合のメリットについて、4つご紹介します。
↓記事と同じ内容と動画でも説明しています。
→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分の動画講座を受け取る
元の音の音量を保って、効果をつけられる

センド方式では、元の音量を保って効果をつけることができます。
インサート方式では、元の音声信号を全てエフェクターに通します。
このため、エフェクターの影響度を高めていくと、元の音声がどんどん小さくなっていきます。
これに対しセンド方式では、元の音声信号から、エフェクターに通す分の音声信号を分岐させます。
そして、エフェクターに通した後の音声を、分岐元の音声と合流させます。
これによって、エフェクターの影響度を高めても、元の音声が小さくなることはありません。
例えば、空間の響きを再現する「リバーブ」というエフェクターがあります。
リバーブは、空間の残響を再現するエフェクターです。
実際に音が鳴っている状態を考えると、「音源から発せられる音」と「壁から跳ね返って後から聴こえる音(残響)」の2つの音が聴こえます。
リバーブは「壁から跳ね返って後から聴こえる音(残響)」の音量や、どのくらいの時間残響が持続するかを調整できるエフェクターです。
このエフェクターの影響度を調整していたら、元々の音である「音源から発せられる音」の音量が小さくなったり大きくなったりしたら使いにくいですよね。
しかし、インサート方式でリバーブを使うと、そのようなことが起きてしまうのです。
具体的には、より響きをよくしたくてリバーブのかかり具合を強くしていくと、ボーカルの音が埋もれて聴こえにくくなる、といったことが起きます。
インサート方式では、エフェクターの影響度を上げていくと元の音は小さくなっていきます。
そのため、どんどん残響がかかってぼやけた音になってしまうわけです。
センド方式を使えば、どんなにエフェクターで残響成分を強くしても、元々の音量に影響を与えることがありません。
そのため、くっきりした音が聴こえつつ、響きのある音が作れるのです。
→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分の動画講座を受け取る
複数のトラックでエフェクターを共有できる

センド方式では、複数のトラックで同じエフェクターを共有することができます。
トラックは、1つ1つの楽器やパートの編集単位です。
インサート方式の場合、1つのトラックにエフェクターを追加していく感じです。
センド方式の場合、トラックからエフェクターに音声信号を送る感じです。
送るから、センド(send、送る)なんですね。
そして、エフェクターには複数のトラックからセンドすることができるのです。
これによるメリットは、トラックが別でも同様の効果を使いたいとき、エフェクターを共有できるので一度の設定ですむことです。
これによって、調整もしやすくなります。
例えば、ボーカル・ギター・キーボードの3つのトラックがあるとします。
空間を再現するリバーブを使うとき、3つの音は同じ部屋で鳴っているため、リバーブのエフェクターは同じものを使った方が分かりやすいです。
「それなら、全てのトラックが最終的に集約される”マスタートラック”にエフェクターを使えばいいんじゃないか」と思われるかもしれません。
しかし、センド方式では各トラックからエフェクターにどれ位の音量を送るかを調整することができるのです。
つまり、トラック毎にエフェクトのかかり具合を調整できます。
これは、リバーブで言えば、「同じ部屋にいるけど、聴く人により近いパートは聴こえやすくしたい」ということを実現できます。
具体的には、
・最も目立たせたいボーカルはリバーブかかり具合を抑える
・バックの音に馴染ませたいパートはリバーブの強めにする
といったことができるのです。
→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分の動画講座を受け取る
パソコンへの負荷を抑えることができる

複数のトラックで1つのエフェクターを共有すると、パソコンへの負荷を抑えることができるというメリットもあります。
インサート方式では、1つのトラックにエフェクターを追加するたび、パソコンへの負荷が上がっていきます。
同じような処理を、複数のトラックにインサート方式で行っていたら、各トラックでエフェクターが起動している状態となります。
そのため、共通化できるエフェクターはセンド方式にすれば、エフェクターの起動が1つで済むます。
これによって、パソコンがデータ処理する量が減ります。
その分、動きも良くなるし、余分なコストがかからなくなって良いです。
→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分の動画講座を受け取る
複数のエフェクターをかけたとき、インサート方式と異なる結果が得られる

センド方式で面白いのは、複数のエフェクターをかけたとき、インサート方式と結果が変わってくることです。
インサート方式では、複数のエフェクターを使うと、直列に繋いでいく感じです。
このため、変化した音にさらに変化を加えるという感じで音が変わってきます。
一方、センド方式の場合は、複数のエフェクターを使うと、元の音に対して複数の変化した音を合成する感じです。
インサートは掛け算で、センドは足し算のようなイメージですね。
これを意識すると、例えばセンド方式で、響き方を変えた複数のリバーブを用意して使うということができます。
響く時間が短いものと、長い時間響くリバーブを用意する感じです。
これによって、1つのリバーブを使うときよりも、よりリアルに空間を再現することができます。
リバーブの重ねがけについては、下記の記事で詳しく書いています。
是非こちらもご覧いただければと思います。
「あなたの曲を本格的にするリバーブを用いたDTMの上達方法」
→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分の動画講座を受け取る
まとめ
ここまで説明してきたように、センド方式でエフェクターを使うと様々なメリットがあります。
センド方式の利点を意識すれば、DTMのテクニックはどんどん向上していきます。
是非、試してください。
僕のサイトではこの記事以外にも、パソコン1台で自由に音楽を作る方法を数多く紹介しています。
ただ、記事数は200を超える量となっています。
そこで、
僕のサイトに載っている知識やテクニックを、順番に見ていくだけで学ぶことができる
DTM作曲に役立つ合計15本・6時間21分を超える動画レッスンを無料でプレゼントしています。
5年以上の時間をかけて僕が培った、DTMの作曲ノウハウをすべて説明した、他にはない大ボリュームの動画レッスンとなっています。
僕自身、専門的な音楽の勉強や楽器演奏の経験の無いところから、社会人になって作曲ができるようになりました。
そのため、一切経験がない方でも安心して見ることができる内容になっています。
作曲に興味をお持ちでしたら、是非チェックしてみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。